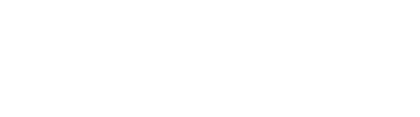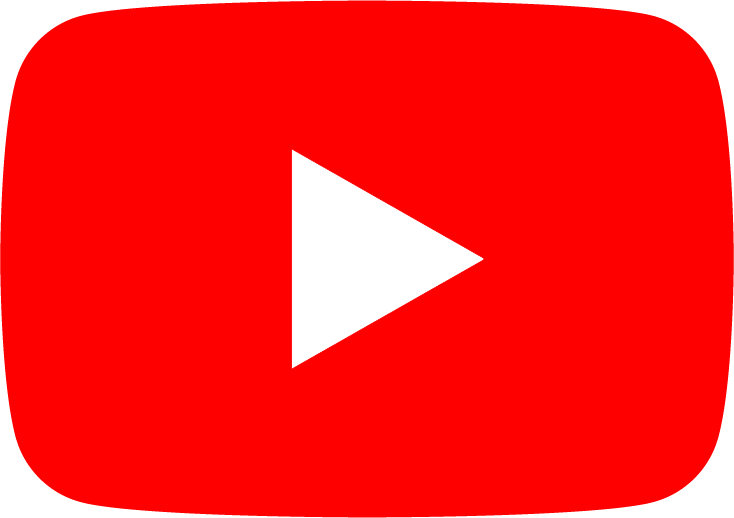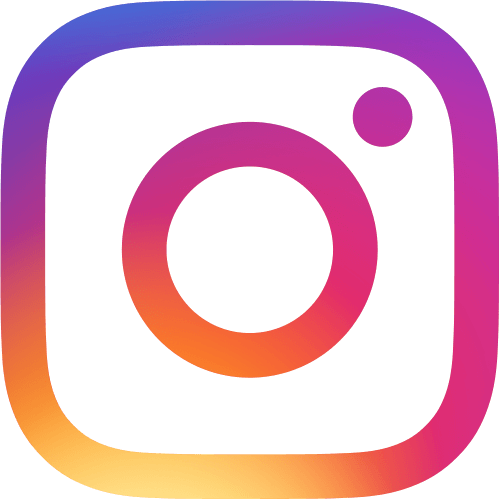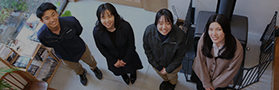1月24日の第217回通常国会にて石破首相が施政方針演説をされました。その中で“国民一人一人が自己実現を図っていける『楽しい日本』を目指す”とありました。これに対して賛否さまざまな意見がされていますね。これって、故堺屋太一さんの『三度目の日本』という本の内容やな!と思った方が多かったのではないでしょうか?
私もこの本を読んだのですが、『明治維新の後に富国強兵を目指した“強い日本”、終戦後に目指した“豊かな日本”、そうして平成の御代を終えこれから目指すべきは“楽しい日本”である』との論説から引用したもの。
でも令和7年1月現在の今にこれが当てはまるのか?現在の日本は、GDPは世界4位、一人当たりGDPでは34位、為替の影響でプッシュ型インフレになってはいるものの、個人所得は横ばいもしくはやや減りの現状で、「楽しいもなにもないでしょう」との反発があったとか。
堺屋太一さんは総務省の国家官僚を経て、経済企画庁長官や経済アナリスト、執筆家としても有名。この著書の中で昭和30年代に計画された東京一極集中の話が多く出てきます。田中角栄の日本列島改造論もその一環だとの爆弾発言もありました。戦争で国土空襲を許し、住宅地も社会インフラもボロボロの状態の中、豊な日本を作るには一極集中が必要だったようです。しかし、高度成長〜バブル崩壊〜失われた30年〜人口減を、令和の今に至るまで一極集中の方針が残ったまま押し通してきた日本。堺屋太一さんが書いたのは、これを次の段階に進めるには“国民一人一人が自己実現を図れる楽しい日本”を目指すべきだ。ということでした。
私は、国民一人一人のことや国政について持論を言うほどの人間ではありませんが、いち地場建築屋として思うのは、“面白い日本”を目指して欲しいということ。
日本全国、いろんな工務店へ出張しながら、様々な街を見て回ってきました。が、どこもかしこも金太郎飴。駅の前にはロータリーがあり、駅前の一等地には生命保険や銀行のビルが建ち、商店街はほとんどシャッターが閉まっていて、住宅地は地域住宅的な家はなく、多国籍どころか無国籍な住宅が立ち並ぶ。
いつも思うのは、日本にきた外国人が喜ぶのは日本の街並み。日本という世界に稀な長い歴史と文化あふれる国柄。播磨に来たら播磨の街並みがある方が良いはず。私にとって“面白い”のは、各地各地にそれぞれの気候風土や人情、歴史を背負った文化がにおう街並みや名物がある日本です。
その地域の木材の手入れ具合や産業としての林業の状態。気候に合わせた軒の出具合や屋根の形。庭に植えられた樹木の植生。土間のあり方、近場の石切場からの石材。何百年、何千年と積み重なった地域の歴史が見える建物群や名産の食品。
例えば、30年前に訪れて、いまだに忘れられない雪国の野沢温泉で食べた野沢菜の美味しさ。江戸時代の街道沿いにある富山おわらの街並み。佐賀県のくどづくりの屋根。冬の南西からの強風に備え、貫と束と呼ばれる梁が重なりながら見える雪国に映えた白壁と共に大きな屋根を支え、非常に優雅でインパクトある外観の吾妻建ちの家並み。鉱物やエネルギー資源が乏しくも、長い歴史あるこの国では、各地の林産資源や食文化が豊かに育っていたのですが・・・。今は全国各地が金太郎飴のように、只々残念な田舎のまちが多い。
各地域のらしさと魅力があふれる“面白い日本”。首相にはぜひ、これを作る!と言って欲しい。これって贅沢なことでしょうか?