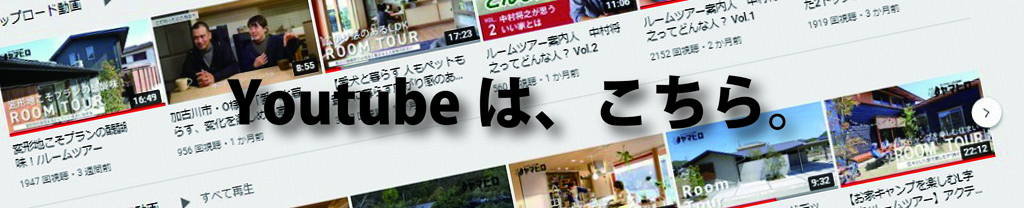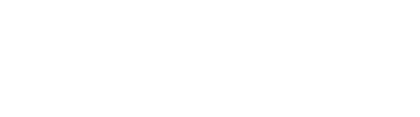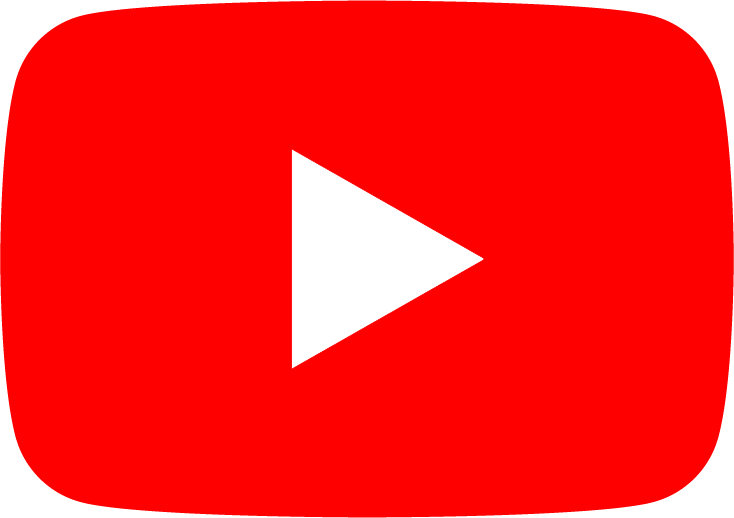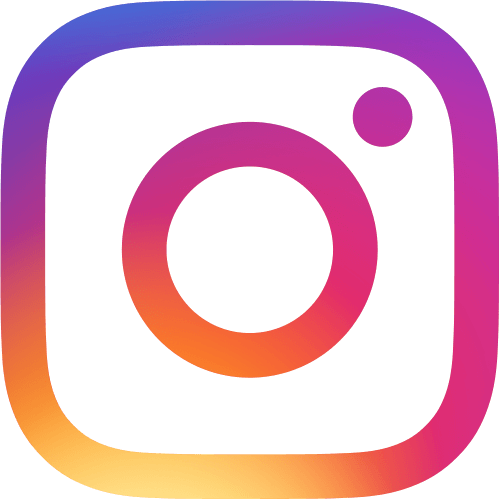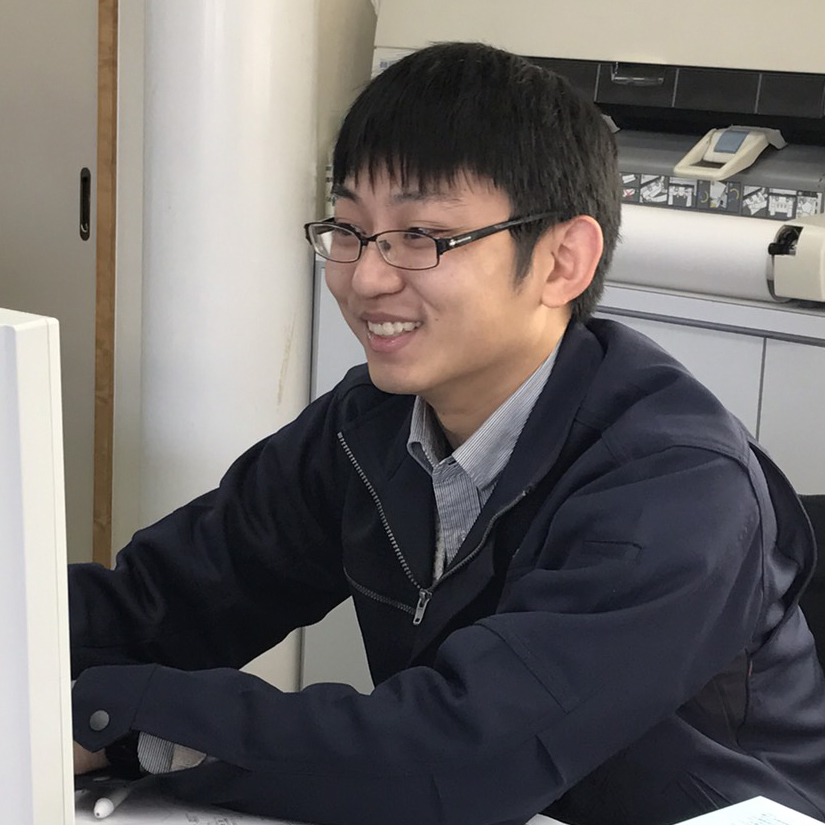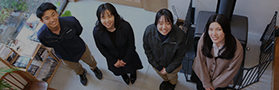こんにちは、管理課の玉中です。
もう半年以上前になってしまいましたが、岡山県の勝央町の町並みを見に行った時のお話です。

勝央町は岡山県勝田郡にある町で、本社のある宍粟市からは車で45分くらいの距離にあります。電車の場合は姫路から龍野・佐用方面に伸びるJR姫新線の勝間田駅が最寄りです。
童話・金太郎のモデルと言われる坂田金時のゆかりの地としても知られています。
以前のブログ『動物に癒される-14』で紹介した『猫に恋する作家展』に行ったのと同じ日の話となります。
過去記事は下のバナーよりどうぞ。
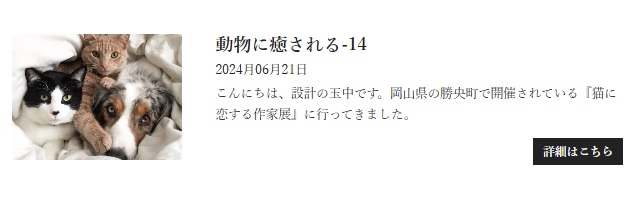
勝央町の町役場に車を止めて、作家展の会場である『勝央美術文学館』からグルッと町並みを見て回ります。
まず見つけたのは江戸時代の偉人・伊能忠敬にまつわる看板です。
日本地図の作成を命じられて各地を旅していた伊能忠敬は1814年に勝央町を訪れ、この地でも天体観測を実施し、勝央町の緯度を割り出したとされています。
この際に宿泊した屋敷と観測を実施した場所が記録されており、偉業を讃えて史跡として残したそうです。
ちなみにこの時の伊能忠敬は69歳。平均寿命が50歳くらいだった時代と考えると、その年で今ほど道が整備されていない中で日本一周をしていた伊能忠敬の凄さが少し分かりますね。
天体観測を行った場所は現在も一般の方の私有地内となっていますが、宿泊した屋敷の跡地は半分ほどが広場で残り半分ほどは古民家リノベを経たコワーキングスペースとして地域で利用されているそうです。


続いては旧勝田郡役所です。
1912年(明治45年)に建てられた赤いトンガリ屋根が特徴的な洋風の木造建築物で、2016年に国の登録有形文化財に登録されています。
かつては役所としての機能が移転された後も勝央郷土美術館として利用されていたそうですが、作家展の会場でもある『美術文学館』の完成に伴って閉鎖され、現在は外観のみ見ることが出来る状態です。
宿場町の名残として江戸時代の面影が強い町なのですが、そんな中にある明治時代の文化を感じさせるこの建物はかなり印象的でした。

これらの伊能忠敬宿泊跡地や旧勝田郡役所は出雲街道沿いにあり、より通行しやすい国道179号が出来た現在も文化的な中心地はコッチだと主張しているような気がします。
出雲街道は出雲大社のある松江藩などが参勤交代で江戸へ向かう際の街道として整備されたもので、勝央町の「勝間田宿」も美作7宿の1つに数えられる交通の要所として発展しました。
出雲街道は石畳で整備されており、道の両側に古い住宅や蔵が点在していて、宍粟市山崎町のさつき通り(一部は通称・酒蔵通り)と似た雰囲気を感じていました。
後で聞くと山崎町の街道整備の際にこの勝央町を参考にしたのだそうです。


この出雲街道沿いの側溝が面白かったので紹介します。
普通は雨水を逃がすためだけど溝なのでコンクリートの蓋やグレーチングなどで通りやすくしていることが多いのですが、勝央町は敢えて側溝を深めに作り、そこに鯉を放していました。



この側溝はところどころネットで鯉の移動を遮りながらも公園の池などと繋がっており、より『通り』として繋がっている感じがしました。


古民家等の古い建物の活用にも力を入れているようで、カフェ&ギャラリーの「あーとゆーや」さんや、年代を感じる寿司と饂飩のお店「篠原かわずや寿司」さん、町役場に隣接する消防署車庫などがあります。




今回は行っていませんが、町内の西部には「勝間田神社」があります。
勝田郡勝央町勝間田にある勝間田神社は住所に『勝』の字が3回、神社の名前も足して4回も入ることから、勝負事に縁起が良いとされています。
加えて、祀られているのは学問の神様・菅原道真です。
これから本番を迎える受験シーズンには持って来いかもしれません。
昨年から山崎の町おこしの集まりにも参加させてもらっており、このような旧宿場町をはじめとする古い町並みへの興味が少し強くなっているこの頃。
また色んなところへ行ってみようと思います。
新築事業部 管理設計 玉中健太
____________________
姫路市・加古川市・たつの市を中心に
兵庫県播磨地域で注文住宅を建てたい方
新築・リノベ・リフォームをご検討の方必見!
____________________
!!!町屋 x アーケード!!!
\町屋リノベーションプロジェクト/

!!!究極の家事動線!!!
\趣味室や大開口など見どころ満載/

!!!通算160万回再生越え!!!
\ヤマヒロYoutubeチャンネル/